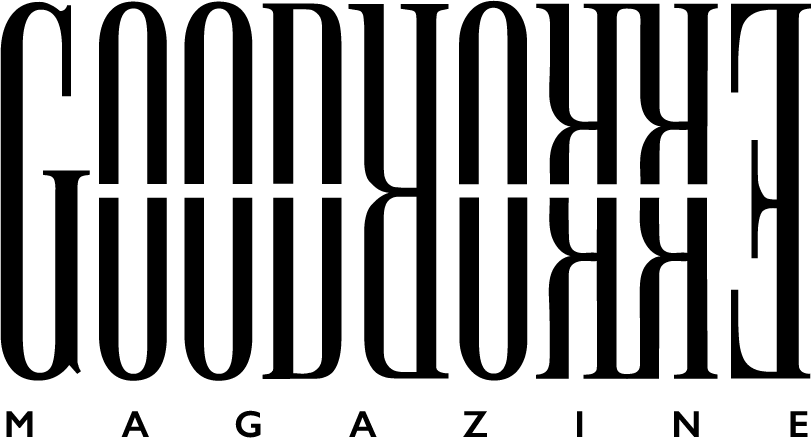YES TO LIFE RISA OKAMURA
「いい帽子被ってますねー」その日のGOOD ERROR MAGAZINE取材班で最年少且つ、モードについても最も無知であろう自分にそんな言葉をかけてくれたのは、ファッション情報番組『ファッション通信』の制作にも携わる岡村理彩。最近はフェルナンド・タティスJr.やカルロス・コレアやピーダーソンなどのMLBのスター選手のユニフォームの着こなしや、身に着けるアクセサリーまでもファッションの視点で追っていたり、とにかくアンテナの張り方が半端じゃない。 そんな彼女とかねてより親交がある、ブランド『Ari』のデザイナー 金子能文 a.k.a KaNe$ (BIGDOGSS)が、岡村をインタビュー。これまでの経歴、師匠との出会い、未来のファッション・ジャーナリストへの金言を訊いた。

◇最後にお会いしたのはいつでした? 2020年の1月にパリのメンズコレクションで「ラフ・シモンズ」を一緒に見ましたね! ◇早速本題に入りたいのですが、まず岡村さんがファッションに興味を持ったきっかけというのは? 小さい頃から、服とか…これ語弊があるかもなんですが、「美しいもの」がすごく好きなんです。服装とか。自分の中の価値観だけなのですが、その「美しいもの」を着ている人をよく覚えてたり、記憶がすごくあるんです。だから自分がそれを持ってなくても「あのクラスメイトの履いている靴はすごく素敵だ」とか。自分が買ってもらえなくて覚えてるものもありますが(笑)、そうじゃなくてもとにかく明確に記憶していて。 ◇それは小学生の頃からですか? そうですね。もっと幼少の頃からですね。例えば「近所の八百屋さんに行きます」とかだけでも、おもちゃのプラスチックのアクセサリーをフル装備で付けて行ったり。本当言うと、いつ何時も靴下と革靴も履いて、完全にドレスアップして出かけたいって感じの子供でした(笑)。とにかく、テレビとか見てても、その内容よりもなんでもその人の身につけているものが気になる。髪型やら服やら。アニメとかでも、ハイジ自身より、クララの白いブーツが気になる…みたいなね。 ◇それはご両親の影響ですか? 母は進学校を卒業した後、「手に職をつけて自立したい」と言うわけで、文化服装学院の、当時の裁断科(現在でいうアパレル技術科)で学んだ後、結婚するまでの数年パタンナーとして仕事をしていました。ちなみに当時、2学年上にデザイン科の学生として山本耀司さんがいて、その姿を見ていたらしいです。彼女から特に何か影響を受けたかはわかりません。が、私自身は「あの子のあの服は素敵」とか「私はこれが好き」とか、服を買いに行くとなると、自分の好みをあれやこれや言ううるさい子供だったみたいです(笑)。言われてみれば父親も「装う」ことに結構こだわりはある方だと思います。加えて「清潔感」っていうのは、かなり二人に教え込まれたかもしれないですね。 中学、高校になってからはファッションに加えて、写真(ファッション系と報道写真)に夢中になりました。社会情勢が気になり過ぎて、小学校の高学年から、高校を卒業するくらいまで、何故か「1面の見出しが大きい新聞」を収集するのが趣味でした(笑)。記事の切り抜きとかじゃないので、物凄い新聞の量……。 ◇その頃からジャーナリズムに通ずることをやられてたんですね。 その頃は何にも考えてはないんですけどね(笑)。インターネットが普及していなかった時代ですから、新聞の大見出しの破壊力と言ったら。ニュースにしかり「事実」とか「そのまま」ということが自分の中では何故かすごく大事でしたね。 ◇高校卒業後から就職まではどうでした? 大学では社会心理学を専攻しました。ジャーナリズムとかそういうのが好きだったので。人はなぜ情報に扇動されるのかとか、社会生活によって起きる影響とかを学びました。大学を卒業後すぐにメディア系の仕事に就きたいと思いましたが、出版社からテレビ局までそれはそれは見事に落ちました(笑)。で、そんな中1社受かったのが損害保険会社でした。 ◇保険屋さんですよね……? はい。損害保険の本社の中枢で予算管理の仕事をしていました。一方で私が所属していた当時の部署(総務部)は「なんでも屋さん」でしたので、株主総会の手伝いもあれば、会社の受付に入ったりと色々でしたね。 ◇それは自分では望まれてない道でしたか? なんて言うんでしょうねぇ。そのままストレートにマスコミ業界に入れたらよかったけど、それが叶わなかったというのもあるし、でも自立するためには働かなくてはいけないですし……。結果的に今振り返ると、社会人としての基礎をここで学べたような気がしています。 ◇その後、会社を退職し、ロンドンに留学されていますよね。 大学1年生のときに短期留学で英国の片田舎に行ったのが初めての海外。単純に、日本の外に出ると、世界を知ることができる。言葉を理解する事で、更に世界情勢がわかるし、何より様々な人種の人たちと混じり合うことができる。それが一番の衝撃でした。その感覚が忘れられなかったですね。次回英国に来る時は短い期間ではなく、もっと長く滞在して学びたいって言うのがありました。


◇留学時代に大変だったことはありますか? 「海外に住む」というのが「人生の一番叶えたいこと」レベルだったので(笑)、結果、何をやっても楽しかったですね。辛いことも全て楽しいみたいな。一生に一回しかないだろうし、自分で選び取ったから、「学費払った分、全て吸収しよう!」くらいの勢いで勉強しましたね。ファッションジャーナリズムを中心に、ファッション概論とか、やりたい科目もてんこ盛りでしたから。と言っても、やっぱり英語の文献を読むとかレポート書くのはしんどかったです。イギリス人の学生は、当然ネイティブだからすらすら読めるわけですよ。そうでない私は、何につけても時間がかかる。とはいえありがたいことに「あまり日本人ぽくない日本人がいる」みたいな感じで面白がられて(笑)。クラス委員とか冗談半分でやらされたり、とにかくイギリス人のクラスメイトにはすごく助けてもらいました。 ◇今の岡村さんにも繋がりますよね。本当どこにでも混ざるじゃないですか。 混ざりますね。混ざりたいんですね(笑)。

◇その後ロンドンを経てパリに行かれるんですよね。 その経緯を聞かせていただけますか? ロンドンに来た時点で「もう少し世界を見たい」と思い始めていました。また、留学する前から母の友人で長年ファッション業界で働いていた人の「英語に加えもう1ヶ国語やったらさらに役に立つ」っていう助言も気になっていて。ロンドンにいて世界を俯瞰してるうちに「もう少し自分は海外にいたいんだ」って明確に思いましたね。 ロンドンでの学生生活が終わる半年前くらいに「今後どうしようか」つまり、どうやってヨーロッパに残ろうかと模索していた時に、たまたま母から雑誌『ハイファッション』(当時、文化出版局が発行していたモード雑誌)に執筆されているパリ在住のジャーナリスト藤井郁子さんの記事が新聞に出ている」と連絡が来て、その切り抜きが送られてきました。そこには白髪の品の良い女性が写っていて。文化出版局のパリ支局員、そして支局長として30年以上にわたって活躍している彼女の記事を、私は長年読んでいました。自分がずっと好きで読んでいた『ハイファッション』。お顔を拝見し、勝手に「あ、もうパリだな」っていうのを直感して(笑)。ファッションの仕事に就くなら…「モードの祭典」とかよく使われるけど、パリを見てみたいって。 そこから、東京の文化出版局に電話をして、藤井さんにコンタクトを取りたいとお伝えし、ご本人からその許可をどうにか取り付けまして、次のステップ、「ご本人に会う」までがまた長い道のりです。 私はまず事前に怪しい人じゃないっていうのを証明するために、自分の履歴書、何故自分が藤井さんに会いたいか、そして何故デザイナーのクリエイションを応援するような仕事をしたいか、っていうのをしたためた果し状みたいな手紙をファックスで送りました(笑)。それからお電話も。すると彼女は「ファックスは拝見しました」と仰られて、私は「お会いしたいです」と言ったんですが、「今はパリコレだから。それにあなたは6月に学校が終わるんだったら、数ヶ月後にお会いしましょう」と言われました。しかし、当時の私はコレクションのサイクルなんてわかっていなかったので、私は少し半ギレ気味に「すみません、藤井さん! 本当に時間ないんですよ」みたいに答えちゃって(笑)。とにかく焦ってたし、ここまで乗り掛かった船だったので。 ◇このチャンスを逃すものか、みたいな(笑)。 そうそう。そしたら「パリコレ終わったら再度電話してください」と言われて。それで約束通り電話をかけてみたら「あなた以前のお電話で時間がないって仰ったわね。じゃあ明日来られるかしら?」っておっしゃるんです。私も「もう夕方で、ユーロスターのチケットも取れてないので、明後日でいいですか?」って答えて。ひょっとしたら藤井さんに試されていたかもしれません。そんなに言うなら、すぐ来られるよね?みたいな(笑)。いずれにせよ、念願叶って彼女のパリのご自宅に向かうことになりました。 お会いしてすぐに、「すみません、弟子にしてください」って頭下げたんですけど。そしたら「私ね、生涯で誰一人、お弟子さんとかとってないのよ」って言われて(笑)。 とは言え、いきなり連絡して押しかけてきたとも言える初対面の私の話を本当に親身になって聞いてくれましたね。自分の中で一番のターニングポイントとなった彼女の言葉が二つあります。私が藤井さんに「ファッション業界って浮ついたイメージがあったのですが、藤井さんのような職人気質で謙虚にコツコツやっている方が何十年も続けられる仕事なら、自分もやれると思いたいです」「自分は残り数ヶ月でロンドンの学生生活が終わります。藤井さんの長いキャリアで培ってきたその目で、今日の私の身なり、話し方、仕草など全てご覧になられて、藤井さんに、ファッションの仕事に向いてないと言われたら、荷物をまとめてすぐに帰国するし、二度とファッションの仕事に手をつけたいとは思いません」と訊いたら、「保証はできないけど、やってみる価値はあるわね。それから、私みたいな人間が長くこの仕事を続けているのだから、あなたの見立ても誤りでないかもしれない」と言ってくれました。そこで霧が晴れたように決心がつきまして、「じゃあ、パリに引っ越します」とお伝えしました。 ロンドンに戻ってすぐ、まだ彼女から弟子入りのOKもいただいてもないのに、両親に電話で「もうパリに引っ越すから」って話してました(笑)。 ◇ご両親は何と仰られました(笑)? 彼らは「この人は海外へ出たら、タダじゃ帰らないだろうな」と薄々は思ってたみたい(笑)。 で、語学学校に通い始めたのですが、藤井さんからは全然連絡が来なくて。「引っ越してきました」とは伝えていたんだけど、数週間は黙々と語学学校でフランス語を学ぶ日々でした。 そしたら9月のパリコレの前日に電話がきて「理彩さん、明日からパリコレがあります。あなた、お手伝いしますか?」と言われて、「やります!」って。 ◇それはウィメンズの取材ですか? 藤井さんは当時、文化出版局を退職され、フリーランスとして活動していましたが、パリのウィメンズ、メンズ、オートクチュールと、パリのファッションウィークのものは全て取材をされていましたね。私は本当に右も左もわからずでしたが「困った時には、私のアシスタントって言いなさい」と言ってくださいました。 私のやることは…約20年前、当時はネットもまだまだの時代だったので、毎日、新聞4紙(「ル・モンド」「リベラリシオン」「フィガロ」「ヘラルドトリビューン」)を必ず買って、その日のコレクションの記事を全部切り抜いて、彼女の家に持って行くとか、藤井さんがスケジュール的に行けない若手デザイナーのショーなどを「勉強になるから」と行かせてくれましたね。自分はその代わりに、それがどう言うものだったかを報告をしていました。 だけど最初の頃は何にも追えてませんでしたね(笑)。「目の前を通るモデルさんの服なんて追えるわけない」と本気で思ってました。無理!本当にビックリしました。座席に座ってて「あ、モデルさんがもう行っちゃった」みたいな。今となっては職業病という感じで、すぐに追えるけど、最初はもうポカンでした。 藤井さんも一応「あの若いデザイナーの方は評判よかったみたいだけど、どうでした?」とかもちろん情報を知りたいわけで、私に訊くのですが、すごい稚拙な返ししか出来ませんでしたね。「えっと…色が綺麗でした」みたいな可哀想な感想しか言えずで(笑)。「もうこれは訓練で、数をこなすしかないな」と思いました。 それから彼女はものすごく几帳面で、コレクションのインビテーションや資料など、大切に保管されていました。今はペーパーレスが主流にはなってはいますが、当時は本当にすごいなぁと憧れの眼差しで見ていました。編集者、ジャーナリストの鏡でしたね。 ◇藤井さんから学ぶことがすごく多かったんですね。 亡くなった時、シラク元大統領夫人からお花が届くくらい、パリのファッション業界でリスペクトされていました。とは言え、ご本人は本当にいつも謙虚でしたね。ある美術館で開催されたエキシビジョンのプレスプレビューに私が鞄持ちで付いて行ったのですが、現地の錚々たるらしき人達が重鎮が「マダムイクコ、こんばんは。今日はよく来て下さいましたね」とか話しかけてくるんです。そうなると、誰かと対面で話すより、自分の気持ちを文章で表現したいくらいのシャイな藤井さんだったので、はにかみながら「理彩さん、もう帰りましょ」とか言ったり(笑)。ご自身がすごい方なのに、こちらがびっくりするくらいに控え目で。そう言うところも本当に好きでしたね。 ご本人は常に謙虚に一歩下がって、業界を冷静に俯瞰して見ていました。そこは自分が彼女から学んだ姿勢でもあります。なので、私は彼女とは対照的に側から見えるかもしれませんが、「輪から一歩下がって冷静に全体を見る。」と言うスタンスは持ち続けていたいですね。 ◇どのくらいの期間、藤井さんに師事されていたのですか? 1年間パリで付いて、みっちり鍛えていただきました。東京に戻ってからも、自分が書いた記事を読んでいただいたり、彼女が帰国する折には必ずお会いしていました。電話もよくしていましたね。 ◇他にも藤井さんから教わったことは? 教えというよりか…彼女は、ああしなさい、こうしなさいと一切言うことないですが、日々の生活を通して身をもって教えていただきました。 それに纏わるエピソードが1つあって…藤井さんが「若手で注目しているデザイナーがいるので代わりに見てきて欲しい」ということで、当時の私は語学学校が終わると直ちに会場に向かったのですが、会場到着が開始時刻の1分後くらいになってしまって。ファッションショーは定時通り始まらないのが通例で、私も既にそれを知っていたんですね。心のどこかにまぁ大丈夫だろう、という油断があったんでしょう。またブランド側もまだショーをするのに慣れておらずで、座席より多めに招待状を配ったようで会場は定員オーバーとなり、扉が締め切られていたんです。私は会場に来ていたアメリカ版『VOGUE』の取材班と一緒に「入れてください」と言えば、ドサクサに紛れて入場できるかもという希望を持って、彼らと訴えたりしたのですが、結果、ダメなものはダメでショー会場には入れず。 先程話したように、私にはコレクション期間中、ほぼ毎日彼女の家にお伺いして、自分が観たショーを報告するミッションがあったのですが、「今日はなんと観ることができていない…怒られるかな」とかなり怯えながら、色々言い訳をこねつつ、最後は立ったままお辞儀して「すみません!観られませんでした」と謝罪すると、師匠は静かに「そうね。ショーに遅れるのはいけないわね」とポツリ。激しく怒られるより、一番心に響きましたね。これ以降はどうにかしてショーの会場には時間前に到着するように心掛けてますし、ほかの仕事でもそれは同様です。一度も私を怒ることなく、“自身が働く姿”で私を導いてくれた藤井さんには本当に感謝しかないですね。永遠の師匠です。 ◇岡村さんはそれを引き継がれたんですね。 そう願いたいです……(笑)。ただ彼女の知性とか品格に追いつくのは相当難しいかと。 ◇先ほど師匠の藤井さんが亡くなられてというお話もありましたが、藤井さんはいつ亡くなられたのですか? 2004年です。私が本格的に仕事をし始めて1年半後くらいですね。 一つエピソードがありまして…。藤井さんのお墓の場所は、なんと偶然にも私が父親並みに慕っていた叔父のお墓の場所と丘の上同士で向かい合わせだったと言う。 ◇すご!鳥肌立ちました。岡村さんのお母様も「ご縁があるんじゃないか」とピンときて、岡村さんに電話をかけてきたし、彼女の記事をロンドンに送ったんですよね。 彼女が亡くなってからそれを知ることになるのですが、驚愕の事実でした。 ◇その後、帰国されるんですか? 1年でしっかりやり切ったと思えたので、東京でキャリアを始めようと。藤井さんにも「帰国したらどうするの?」と聞かれたんですけど、「私は自分の力で仕事を探します」と伝えて、日本に帰ってきましたね。 ◇それで、どんなお仕事をされたんですか? 帰国後数ヶ月で『WWDジャパン』(INFASパブリケーションズ)に採用していただきました。就職活動を必死にやりましたね。 ◇『WWDジャパン』ではどんな仕事をされていたのですか? 当時、コレクション班という、コレクション取材をメインにすると言うチームがありまして、そこに配属されました。と同時に、その当時あったコレクションマガジン『ファッションニュース』の2媒体をやってください、と言われました。昼間は『WWDジャパン』夜は『ファッションニュース』みたいな感じで、そういう二刀流ですね(笑)。 ◇すごい仕事量ですよね。なんとかこなせてたのですか? 本当に駆け出しだったし、藤井さんと出会ってからは「藤井さんのような人間になりたい」という目指すところがあったので、しんどくても、結果、楽しいんですよ。あまり出来が良い記者、編集者ではなかったかもしれませんが(笑)。 当時は全然デジタルの時代でもなかったので、海外のカメラマンが送ってくれた、何百枚もあるコレクションの写真のネガをビュワーで観るだけでも延々とやってられるみたいな。 ◇本当にファッションが好きなんですね。 もうここまでくるとあまり意識もないんですけどね(笑)。「記事を書く」とか「『ファッション通信』でこういうの取り上げたらいいんじゃない」とか、自分は完全に「見る側」の立場。そんな自分からしたら、「手からモノを創れる人はヒーロー」なんですよ。そういう人達に会えるって言う。彼らの世界を見せていただくって言う。それは楽しいに決まってるでしょ(笑)。そうじゃないって言う人も世の中にはいるとは思いますが、自分はそうです。 ◇岡村さんはいつも楽しそうにされてますよね(笑)。 はい、単純!!です(笑)。 ◇今まで本当に多くの取材をされてますよね。 海外のコレクションの取材だと、日本からの動画媒体が我々のメディア『ファッション通信』だけということも多々あります。ショー会場で手短にお会いしたお話した、と言う数も含めたら、それなりの人数のデザイナーの方や、ジャーナリスト、クリエイターの方などにお会いさせていただいたかもしれませんね。 ◇その中でも印象的だったデザイナーやアーティストはいますか? うーん…取材させていただいたシチュエーションにもよりますから、甲乙つけがたい…..です! 2010年にアレキサンダー・マックイーンが亡くなった数日後にNYコレクションが始まって、いろんな人から追悼コメントを撮ったんですね。ジャーナリストを始めデザイナーの皆が、取材しているこちらが思わずもらい泣くくらいの言葉を聞いた時「これはただ事ではない」と実感しました。 また仕事を始めて(WWDジャパン時代)最初にインタビューしたのは、ポール・スミスで、すごく嬉しかった覚えはあります。細部まですごく気配りができる方という印象でしたね。多くのデザイナーの方にインタビューをさせていただきましたが、あ!…カニエさんも(笑)。 ◇今話題のイェさんですね(笑)。 イェさんは穏やかな人っていう印象でしたね。「YEEZY(イージー)」のデビューコレクションの直後にバックステージでインタビューしました。スニーカーについて聞いた時に「1足のスニーカーが発端となって、犯罪や暴動が起こるんだから、スニーカーの持つ威力は圧倒的」と。 ◇日本のデザイナーではどうですか? 1度だけですが、物凄い存在感を感じたのは、山本耀司さんです。 ◇若手のデザイナーが成長していく過程を見るのはいかがでしょうか? 若手の方が着実に成長されて、もうお話できないくらい遠くになりすぎた、とかそういうストーリーはいいですねぇ。

余談ですが、私は仕事に関して「これは華やかだからやりたい」とか「これは地味だからやりたくない」みたいな喰わず嫌いは持たないようにしています。もうかれこれ20年前近くになりますが、藤井さんが「これからは一つのことだけを究めるのではなく、何でも色々やるのが大事ですね」っていう言葉をよく思い出します。

◇これからファッションの仕事に携わりたいって言う人たちにメッセージをいただけますか? 外の世界を見るには語学のスキルがあったほうが役には立つかな……と。これは特に海外の取材で学んだことですが、自分が仕事を始めた時の約20年前より、今の方が「社会情勢とファッション」の繋がりはさらに密接になっています。私があえて言う事でもないですが、SDG’Sはもちろん、ダイバーシティとインクルージョンなど一連の流れを始め、「ファッションの仕事に従事することは、世界情勢を体感すること」とも言えます。その情勢を自分の目で見て、理解するにも英語は重要ですね。完璧な英語でなくてもいいのです。外の人と自分の言葉で仕事をしていくと、何かの可能性が開かれるかと思います。 なんか「努力したらなんでも叶います」とかではないような気もするんですよね。私も今は気がついたら『ファッション通信』を始め、動画をメインにした仕事をしています。世界のコレクション取材だけを中心、ではなく、単発でPVみたいな動画を作っていたりもしますし、原稿も書いたりしますし、何でも屋さんです。今では目の前にあること、そして自分が面白いと思ったことに全力で乗っかっていくみたいな状況になっています(笑)。 また、誰かに「なんかやってください」って言われた時に、とりあえず「Yes」と言っとくことも大事かもです。断らないで「やります」とその話にのっていたら、どうにかなっていく。 ◇俺たちは「No」って言いがちですけどね(笑)。 できないかもしれないけど、とりあえず「Yes」と言ってから考えるみたいなところがあります(笑)。その後に「このスキル足りないな」と思ったら、そのスキルを持っているブレーンの方を探して引っ張ってくればいいじゃないって思う。私は知らないことを知るために、自分とは違うジャンルの人たちに会うようにしています。それに精通してる人から教えてもらう情報は、すごい勉強になります。要は、自分が知らないことが多いから、いろんな人の引き出しで補って生きてるんです。 後は一昔前に比べて今は、更に「明確な正解がない時代」のような気がします。自由度が増したと言うか。なので、自分と対話をしながら、自分の答えを見つけてみるって言う事ですかね…。コレをやったら自分にとっては「心地よい」ってことを1つずつ潰していく。私の場合は「ファッションが好きだ」「ジャーナリズムをやりたい」「海外に行ったら楽しいだろう」と自分の中の正解を1個1個潰していったんですよね。失敗をかなり繰り返しながら(笑)。今もなんだかんだと毎日手探り過ぎて、全く終わりが見えていないです。 ◇深っ!深いですね。まとまりました。 岡村さんのように夢を追って突き進める人もあまりいないから、本当すごいなって思います。

「気づいたら続いていた」っていう(笑)。金子さんがずっとダンスを続けているように。タイミングとか色々が重なったこともあるし、あとは何故か「海外に住む」って言うことが人生で一番叶えたいことって本気で思っていて、それを実現させてから何かが開いて行った気がします。 ◇好きなことに突き進んでいくのって覚悟も伴ってくるとは思うんですけど、岡村さんの場合は、好きの純度が高すぎて…覚悟を上まってますよね。 上回っているっていうかもう自分ではわからないですね。いずれにしても今の仕事(番組取材から、撮影などの映像制作も含めて)皆でワイワイ作る、文化祭のような空気が大好き。自分が思う夢の世界を創ってくれる方々は、自分にとっては本当にスターみたいな存在ですから、もうそれだけで楽しい。とにかく「モノを創れる人たち」に対するリスペクトが溢れ出ちゃっています。自分にはできないことですから。あと「美しいもの」って癒しですし、いつでも胸が打たれます。だって「ラフ・シモンズ」見てお互い感涙したじゃない! ◇感涙しましたね。でも毎回、感動するんですよね。 一期一会じゃないですが「このチャンスを逃したらもう二度とない」と思ったら、誰でもどんな馬力でも出ると思う。例えば、取材の現場で、これは「もう二度と見られない」って思ったら、どんなこともできる。そういうマインドは大切にしています。 でもそれと同時に切なさもすごく感じるところはあります。海外のコレクションの取材が頻繁だった頃、毎回同じ場所に行き続けていると、例えばホテルの人とか、会場の警備員のおじさん、果ては現地のプレスまで色々と覚えてくれることがあります。特にコロナ禍以前は「じゃあリサ、今度9月に会おうね」とか何か当たり前のように言われる場合があるのですが、次回があるかないかは全く未知数。なので、その時ごとの出会いに、良くも悪くも悔いを残さないようにっていう気持ちを持っています だから、コロナが始まって海外の取材に行かなくなってから、現地でお世話になった様々な人のことを思い出します。「NYのあの人は、ロンドンのあの人はどうしてるんだろう」と。それを思う時に、究極言えば、その人はもう亡くなってるかもしれないけど、会っていた時、自分なりのやり方で全身全霊かけて良い時間を共有できたはず……とか考えたりしますね。 このマインドを持つきっかけになったのは…大学1年生のときの短期留学した英国で出会った同じ歳のスペイン人の女の子。彼女とは、その時別れ際に「数年後、卒業旅行でスペインに行くね」って約束しました。でもその翌年に、その子が交通事故で亡くなっちゃって。それを知らせるために彼女の両親からクリスマスカードが送られて来たのですが、カードと一緒に、亡くなる直前に彼女が書いたという私宛の手紙が添えられていました。その中に私に「すぐに本当に会いたい」と書いてあって。それで、生前彼女のもとへ行かなかったことをすごく後悔しました。彼女はファッションがすごく好きで、本当にお洒落な人だったので、コレクションとか海外出張に行く際は、御守り代わりに彼女の写真を絶対に持ち歩いてます。 だから、人生は「賭け」みたいなもので、生きてることが奇跡だと思ってます。

PROFILE 岡村理彩 | Risa Okamura 1974年東京生まれ。 東洋英和女学院中学部、高等部を経て、東洋英和女学院大学卒業。 住友海上火災保険(現・三井住友海上)に勤務。 その後渡英し、London College of Fashionにて学ぶ。 パリに渡り、語学勉強をする傍ら、パリ在住のファッションジャーナリスト 故・藤井郁子氏に師事。 帰国後 ファッション週刊誌『WWDジャパン』 雑誌『FASHION NEWS』『流行通信』を経て 現在は番組『ファッション通信』の制作を始め、ファッションドキュメンタリーの制作や、PVのプロデュース、執筆などを行っている。
Interview :Yoshibumi Kaneko Text : Yasushi Kishimoto Photo : Yusuke Baba